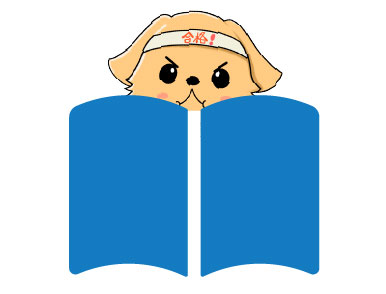2026 川崎医科大学の特徴

📌 大学の「目的・教育目標」
目的・使命:
社会の要請に応え得る有能な医師を育成。
医師としての人間愛、知性、道徳性、意志・体力、医学知識の深究を重視。
教育目標:
患者から信頼される、人間性豊かな医師
幅広い知識・技能を持ち、心優しく有能な医師
全人的医療と専門性を兼ね備えた医師
研究マインドを持ち、医学の発展に貢献できる医師
教育の特色:
6年間一貫した医学+人間教育
基礎と臨床の統合授業
小グループ制のきめ細かな指導
**全寮制(1年次)**により共同生活を通じた成長
チュートリアル教育で問題解決力を養成
診療参加型実習で現場に強くなる
豊かな自然環境と充実した施設・寮・教員陣による学びやすい環境
🌟個性と魅力
川崎医科大学の強み
1. 「人間教育」を重視した全人的医師養成
医師としての倫理観・共感力・人間性を重視し、共同寮やチュートリアル学習を通じて人間的成長を促します。
2. 基礎と臨床の融合教育
初年度から臨床ともつながる授業を実施し、実践的学びと基礎知識の連携を強固にします。
3. 少人数教育によるきめ細かい指導
小グループ形式で教員や同期と濃密な交流・協力ができる教育体制を整備。
4. 診療参加型実習で “使える医師” を育てる
実際の医療現場での参加型実習が早期から導入され、現場力・臨床力を着実に養成。
5. 研究マインドを備えた次世代医師
学部から研究意欲を育てるカリキュラムを用意し、研究と臨床両面を担える人材を育成。
6. 充実した学習・生活環境
- 緑・自然あふれるキャンパス、最新設備、全寮制の環境によって、学びに集中できる場を提供。
川崎医科大学の「人間をつくる」「診療参加型実習」「全寮制」などの特徴的な取り組みについて、実際の学生や大学の取り組みから得られる具体的なエピソードを以下にご紹介します。
🏠エピソード01
全寮制による共同生活
1年生は全寮制(全室個室+食事付き)
1年次は男女別、全室個室で寮生活。朝夕の食事が提供され、共同の食堂・談話スペースを利用でき、生活リズムと学習の基盤が整う環境です。
寮には舎監・寮母もおり、夜間やメンタル面も安心のフォロー体制が整っていることから、新入生にとって心強いスタートになります。
出身地や年齢が異なる学生たちが寝食を共にすることで、チーム医療に必要な協調性・規律意識・コミュニケーションスキルが自然と養われるとされています。
寮生活の規律も教育の一環
- 朝は課題配布や朝礼があり、夕方には部活への参加が義務付けられるなど、時間管理と集団行動の大切さを実地で学ぶ機会があります。
🩺 エピソード02
初年次からの臨床体験と診療参加型実習
1年次に行うEarly Exposure(早期臨床体験)
視能訓練士の現場見学を通じて、患者対応を観察・メモする姿勢から医療職への自覚が芽生えるといったエピソードがあります。
その際の経験を、後日のグループワークでKJ法を用いてまとめ、チームで考察する実習も実施。早くもチームワークやプレゼン力が育まれます。
5〜6年次には診療参加型クリニカル・クラークシップ(CC)
2〜4週間単位で各科をローテーションし、医療チームの一員として実際の診療計画に携わる経験を積みます。
最終年では、担当科で3ヶ月以上臨床実習を行い、Post-CC OSCE試験に合格することで、臨床能力が客観的に評価される仕組みが設けられています。
🌱 エピソード03
少人数チューター制度+自習環境
1〜3年/4〜6年の縦割りチューター制度を導入し、教員および先輩学生が学習面や生活面の相談に親身に対応します。
学年別の個別自習室が用意されており、友人や先輩との情報交換・学び合いが自然に促進される環境です。
💡 エピソード04
その他の注目エピソード
ドジョウ実習では、1年次に徹夜でドジョウの発生・行動を観察し、「体力・集中力・生命への理解を育む」医学教育独自の経験が紹介されています。
解剖実習を2回実施:1年次で人体構造理解のため、5年次で臨床解剖実習と、段階的に技術・知識を深めるユニークな構成です。
附属病院は日本初のドクターヘリ運用など先進的医療教育環境を備え、リアルな医療現場で学ぶ姿勢を育てます。
🌟 教育の質と学生の成長を支える体制
共同寮による人間力の土台作り
→ 規律・協調・コミュニケーション能力が自然に身につく。初年次からの臨床接触による実学重視
→ 医療現場が早くから学生の学び場となる。診療参加型で実践力の修得
→ 医療チームの一員として参加し、即戦力としての自覚を醸成。少人数制+チューター制度によるきめ細かなサポート
→ 学習・生活面の相談がしやすく、心理的安心感がある。学びやすい施設・環境(自習室、最新実習設備)
→ 自主学習がしやすく、学習意欲が自然と高まる設計。
これらのエピソードは、川崎医科大学が「人間性・実践力・自律性」を重視し、多様な学びの機会を通じて自分自身を成長させる場を提供していることを示しています。志望理由書では、自らがどのようにこれらの環境を活かして成長したいかを具体的に述べると強い印象を与えやすいでしょう。
さらに、「ドジョウ実習の苦労と達成感」「早期臨床体験で感じた医療の現場のリアル」など、ご自身で調べた具体的な経験や感じたことを織り込むと面接でも説得力が増します。