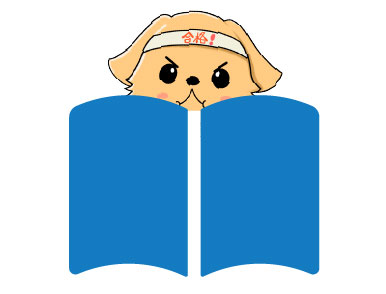2026 東京医科大学の特徴

📌 大学の基本情報・立地
東京医科大学は、大正5年(1916年)に創立された歴史ある医科大学です。「自主自学」を建学の精神に掲げ、常に時代の変化に対応し、最高水準の医療人を育成することを目指しています。特に、2019年に新大学病院が開院してからは、最先端の施設での学習環境が整備され、さらなる教育・研究の充実が図られています。東京医科大学は、都心に位置するキャンパスと、地域の基幹病院としての役割を担うキャンパス、そして救急医療に特化したキャンパスを持つ、特色ある大学です。医学部医学科の学生は、1・2年次は東京医科大学キャンパス(新宿区)、3~6年次は東京医科大学病院がある西新宿キャンパスで学びます。
キャンパスとアクセス
新宿区に位置する東京医科大学キャンパスでは、一般教育科目や基礎医学を学びます。構内には人工芝のグラウンドや体育館が併設されており、活発な部活動が行われています。また、新大学病院に隣接する西新宿キャンパスでは、3年次から臨床医学を、4年次からは臨床実習が本格的に始まります。最先端の医療現場を間近に感じながら、医師としての心構えや知識、技術を学ぶことができる点が大きな魅力です。
茨城県稲敷郡阿見町にある茨城医療センターは、地域医療に興味を持つ学生にとって貴重な学びの場です。八王子市にある八王子医療センターは、救急医療に特化しており、多様な医療ニーズに対応する附属病院を有しています。これら3つの附属病院が連携することで、幅広い医療分野の実習機会が学生に提供されています。
住所
東京医科大学キャンパス:〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1
アクセス
JR、小田急線、京王線:「新宿駅」東口または中央東口から徒歩約20分
丸ノ内線:「新宿御苑前駅」2番出口より徒歩約7分
副都心線・都営新宿線:「新宿三丁目駅」C7出口より徒歩約10分
都営バス:新宿駅西口から練馬車庫前行「新宿一丁目北」より徒歩約3分
🌟医学部医学科の教育の特徴
教育理念と目的
東京医科大学の教育は、建学の精神である「自主自学」に基づき、学生が自ら課題を発見し、解決する能力を養うことを重視しています。特に、学修成果基盤型教育(コンピテンシー・ベースド・エデュケーション)を導入しており、6年間で身につけるべき教育到達目標が明確に定められています。
「患者とともに歩む医療人を育てる」というミッションを掲げ、このミッションを遂行できる医師を育成することを目的として、医学教育プログラムを編成しています。
各学年の特徴的な教育内容
1年次、2年次: 医学の基礎を学ぶだけでなく、「自己と他者」の関係性を考えるための人間学や、協働して課題を解決する力を養うためのPBL(問題解決型学習)や多職種連携教育が行われます。特に、基礎医学統合演習では、基礎医学の概念を学んだ後、実際の症例検討を行うことで、早い段階から基礎と臨床を結びつける力を養います。また、反転授業や少人数教育、シミュレーションなどの手法を取り入れた授業により、学生が主体的に学ぶ環境が整えられています。
3年次、4年次: 臨床医学・社会医学系の科目が中心となり、オンデマンドと対面演習を組み合わせたハイブリッド型受講形態が採用されています。これにより、学生は自分のペースで学習を進めることができ、学修意欲のある学生は、2022年度から導入された少人数ゼミ形式の演習「自由な学び系科目」に参加し、研究や地域医療、USMLE受験準備など、自身の興味に応じた能動的な学びを深めることができます。
5年次、6年次: 診療参加型臨床実習が本格化します。学生は指導医の監督のもとで診療に参加し、実践的なスキルと知識を習得します。また、第6学年の4月には、海外の大学・病院で1か月間の臨床実習が必修となっており、世界トップレベルの医学に触れることで、国際的な視野を持つ医療人を育成することを目指しています。これは、グローバルな医療現場で活躍できる人材を育成するための、東京医科大学独自の取り組みの一つです。
このように、東京医科大学では、建学の精神である「自主自学」を実践するために、学生が主体的に学ぶ「能動的学習」を重視しています。単に知識を詰め込むだけでなく、自ら考え、問題解決能力やコミュニケーション能力、そしてチームワークを培う教育を展開していることが大きな強みです。
🏠学生生活・施設環境
部活動
体育会系と文化会系を合わせて多くのクラブ・サークルが活動しており、学生生活を彩る重要な要素となっています。クラブ活動などを通じて、先輩後輩や看護学科の学生との交流も盛んで、学年や学科を超えたコミュニティが形成されています。単に運動や文化活動を楽しむだけでなく、臨床の現場での知識や手技を磨く団体、一般の方々に心肺蘇生を普及させる活動をしている団体など、医科大学ならではの活動も行われており、学生たちは勉学以外の面でも主体的に活動する機会を得ています。
大学の周辺環境
新宿という都心の中心部に位置しているため、学生生活の利便性は非常に高いです。買い物や食事、文化施設へのアクセスが良く、放課後や休日の時間を有意義に過ごすことができます。一方で、キャンパス内は学習に集中できる静かで落ち着いた環境が保たれており、都心にありながらメリハリのある学生生活を送ることが可能です。
先輩後輩の関係
クラブ活動や担任制度、相談教員制度を通じて、先輩後輩の結びつきが強いことが特徴です。特に、相談教員制度では、担当教員が先輩として親身に学生の相談に応じ、助言をしてくれるため、学習面だけでなく生活面での悩みも気軽に相談できる環境があります。このような縦のつながりが、学生たちの不安を軽減し、学業に集中できる一助となっています。
医学に関係した学習環境
2019年に開院した新大学病院は、国内初の「ロボット手術支援センター」を設置するなど、最先端の施設を備えています。学生は、この附属病院に隣接する西新宿キャンパスで学び、常に医療の現場を感じながら実習に臨むことができます。また、茨城医療センター、八王子医療センターといった特色ある附属病院での実習機会も豊富にあり、地域医療や救急医療といった多様な医療分野を体験できる学習環境が整っています。
🩺 在学生・卒業生の声
実際に東京医科大学医学部医学科で学ぶ学生たちや卒業生からは、大学の教育や環境についてどのような声が上がっているのでしょうか。公式サイトに掲載されたインタビューから、一部をご紹介します。
在学生の声
「多職種連携を早くから学べる」
1年生から他の医療系学部の学生と連携して学ぶ機会があり、チーム医療の重要性を早い段階から理解できます。将来、様々な専門職と協力して働くことを見据えた教育は、非常に有益だと感じています。
「先生との距離が近く、質問しやすい」
少人数教育や担任制度のおかげで、先生方との距離が近く、わからないことがあればすぐに質問できる環境です。熱心に指導してくださる先生が多く、安心して学習に取り組めます。
卒業生の声
「最先端医療を体験できる充実した臨床実習」
新しくなった大学病院での臨床実習は、最先端の医療技術を間近で見学・体験できる貴重な機会でした。特にロボット手術支援センターでの経験は、将来のキャリアを考える上で大きな刺激となりました。
「海外での臨床実習が、医師としての視野を広げてくれた」
必修となっていた海外での臨床実習は、日本の医療とは異なる文化や医療システムに触れることができ、医師としての視野を大きく広げる経験でした。グローバルに活躍したいという思いがより強くなりました。
🌱 どのよう医師を目指す人に向いているか
以上の特徴を踏まえると、東京医科大学医学部医学科は次のような志望者に特に適した環境と言えるでしょう。
能動的に学習したい人
授業形式が反転授業や少人数教育、PBLなど、学生が主体的に学ぶことを重視しています。受動的に講義を聞くだけでなく、自ら考え、議論し、発表する力を身につけたい人には、非常に適した環境です。
国際的な医師を目指している人
6年次には海外での臨床実習が必修となっており、グローバルな視点を養うことができます。将来、国際的な医療現場で活躍したいという明確な目標を持つ人にとって、このプログラムは大きな強みとなるでしょう。
幅広い医療分野を学びたい人
都心にある大学病院に加えて、地域医療に特化した茨城医療センター、救急医療に特化した八王子医療センターという3つの附属病院での実習機会があります。特定の分野だけでなく、多様な医療現場を経験したい人に適しています。
向いていない可能性がある人
受動的な学習を好む人:アクティブラーニングを重視しているため、受け身の姿勢では学びを深めることが難しいかもしれません。自ら積極的に参加し、発言することが苦手な人には、教育スタイルが合わない可能性があります。
特定の分野に特化して学びたい人:幅広い医療分野を経験できる反面、早期から特定の専門分野に絞って深く学びたいという志向の人には、カリキュラムの進め方が合わない場合もあります。
東京医科大学医学部医学科は、「自主自学」の精神に基づき、患者さんと共に歩む医療人を育成することを目指しています。都心という好立地でありながら、最先端の医療施設と多様な附属病院での実習、そして国際的な視野を養うためのプログラムが充実していることが大きな魅力です。自ら学びを追求し、人間性豊かで実践的な医師になりたいと願う人にとって、この大学は理想的な舞台となるでしょう。